
目次
障害が重い利用者に対して質の高い介護サービスを積極的に提供する事業所では、特定事業所加算を算定することができます。
特定事業所加算を算定できる事業所に「同行援護」が挙げられます。同行援護では、視覚障害や知的障害、精神障害のある利用者が外出する際に外出先に同行して道案内など必要な支援をおこなうサービスのことです。
同行援護において特定事業所加算の算定をおこなうためには、厳しい算定要件を満たす必要があります。
この記事では、同行援護の特定事業所加算について、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえたうえで算定要件を解説していきます。
令和6年度の改定によって、同行援護の加算要件が見直されました。改定後は、専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所を評価できるように、加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介助員であり同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置割合が追加されています。
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
サービス提供体制の整備には、以下の6つを満たす必要があります。
良質な人材の確保には、以下の5つを満たす必要があります。
重度障害者への対応は、以下を満たしている必要があります。
中重度障害者への対応は、以下を満たしている必要があります。
特定事業所加算Ⅰは、要件のうち「サービス提供体制の整備」「良質な人材確保」「重度障害者への対応」の3つを満たすことで、所定単位数の20%を算定できます。
特定事業所加算Ⅱは、「サービス提供体制の整備」と「良質な人材確保」の2つの要件を満たすことで、所定単位数の10%を加算できます。
特定事業所加算Ⅲでは、「サービス提供体制の整備」と「重度障害者への対応」の2つの要件を満たすことで、所定単位数の10%を加算できます。
特定事業所加算Ⅳでは、「サービス提供体制の整備」と「中重度障害者への対応」の2つの要件を満たすことで、所定単位数の5%を加算できます。
| 満たす必要がある要件 | 加算 | |
| 特定事業所加算Ⅰ |
| 所定単位数の20% |
| 特定事業所加算Ⅱ |
| 所定単位数の10% |
| 特定事業所加算Ⅲ |
| 所定単位数の10% |
| 特定事業所加算Ⅳ |
| 所定単位数の5% |
同行援護で特定事業所加算を取得することのメリットを2つご紹介します。
同行援護の特定事業所加算の算定は、事業所全体でおこないます。そのため、すべての利用者の総単位数が5〜20%アップします。
特定事業所加算の算定をおこなうことによって、事業所の経済的な負担が軽減されるだけでなく、職員に対してほかの事業所よりも多くの給与を支払うことができます。職員の採用時にも、給与など他の事業所との差別化を図ることができるでしょう。
特定事業所加算は、必要な体制が整備され、質の高いサービスを提供する事業所を評価する加算であるため、この加算を算定できること自体が質の高いサービス事業所と認定されていることになり、利用者に向けても質の高い事業所であることをアピールすることにつながります。
同行援護で特定事業所加算を取得することには以下のデメリットもあります。
特定事業所加算を受けるためには、追加の手続きや書類の提出が必要な場合もあります。これによって事業所の業務が複雑化して、時間がかかったり、労力負担が大きくなったりする可能性があります。
特定事業所加算を取得する際には、厳しい要件を満たす必要があります。要件の確認を怠り運用をすると数百万〜数千万円の返還を求められる場合もあります。正しく要件を理解して運用しましょう。
また、要件を満たすために事業所が追加の負担を負うことになる場合もあります。また、特定事業所加算を受けることで他の助成金や補助金の対象外となることもあるので、注意が必要です。
特定事業所加算を同行援護事業所が算定する際の注意点は以下の通りです。
指定事業ごとに要件を満たす必要がある居宅介護、重度訪問介護、同行援護の指定をそれぞれ取得する事業所が多く、特定事業所加算もそれぞれ取得するケースが多いです。
ここで重要なのが、それぞれの事業ごとに特定事業所加算の要件を満たしたかどうかを毎月確認することが必要です。同じ事業所であっても、居宅介護、同行援護ごとに、特定事業所加算の条件を満たさなければなりません。
算定にあたっての要件は厳しいですが、運用開始できると、収益アップが見込める体制を構築できることに加えて、ほかの事業所よりも質の高い事業所であることをアピールすることができます。利用者が質の高いサービスを受けられるだけでなく、働く職員にとっても給与などの処遇改善が望めるでしょう。ぜひ特定事業所加算の取得をご検討ください。
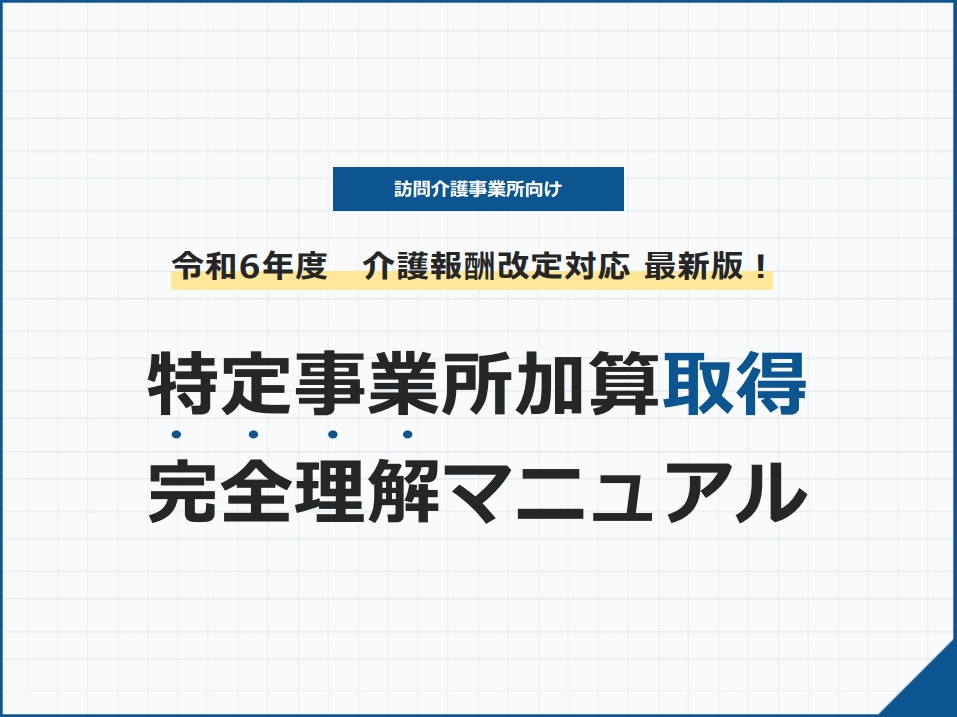
関連記事

特定事業所加算
【令和6年最新版】訪問介護における特定事業所加算の算定要件とは
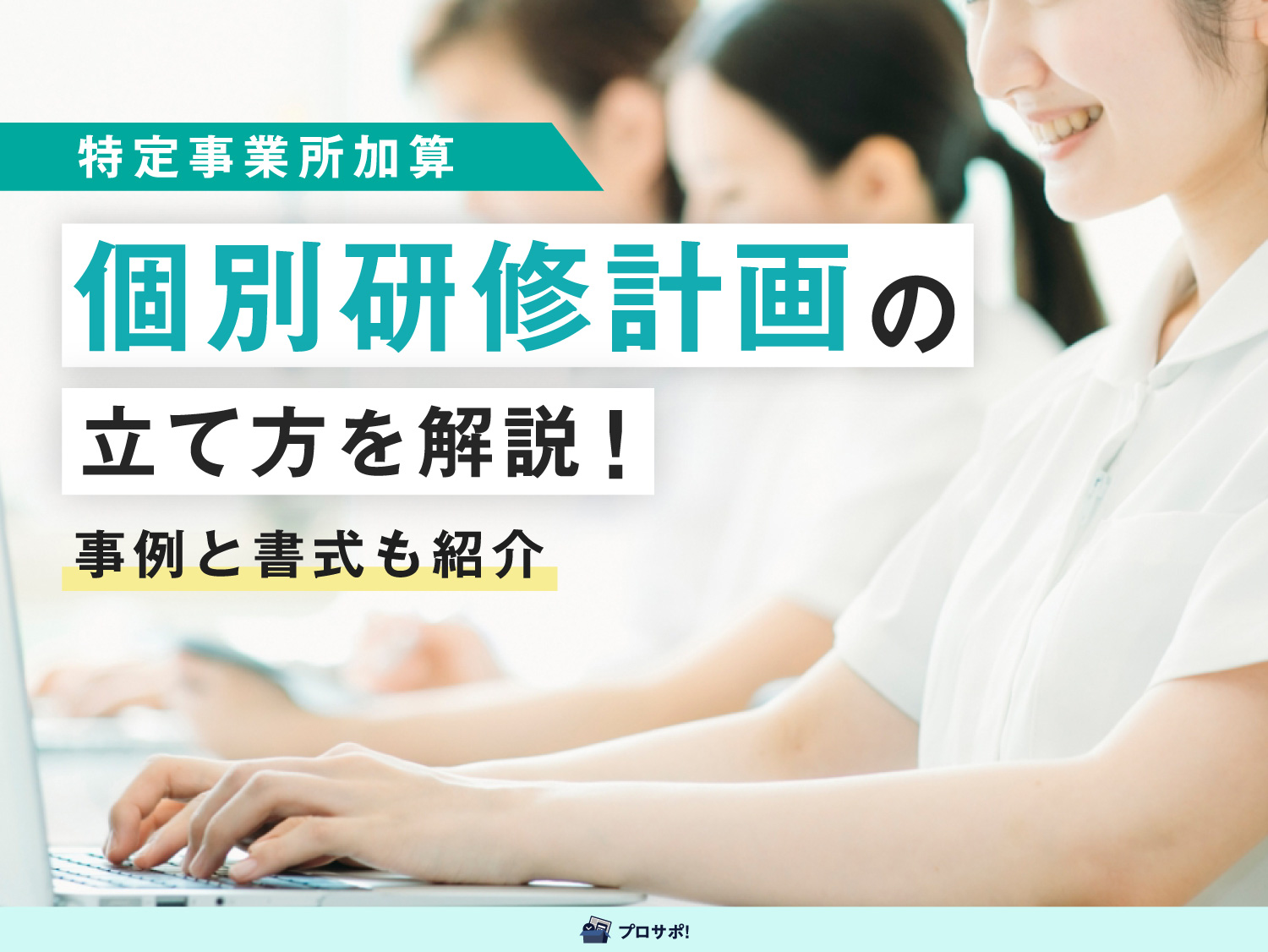
特定事業所加算
【特定事業所加算】個別研修計画の立て方を解説!事例と書式も紹介
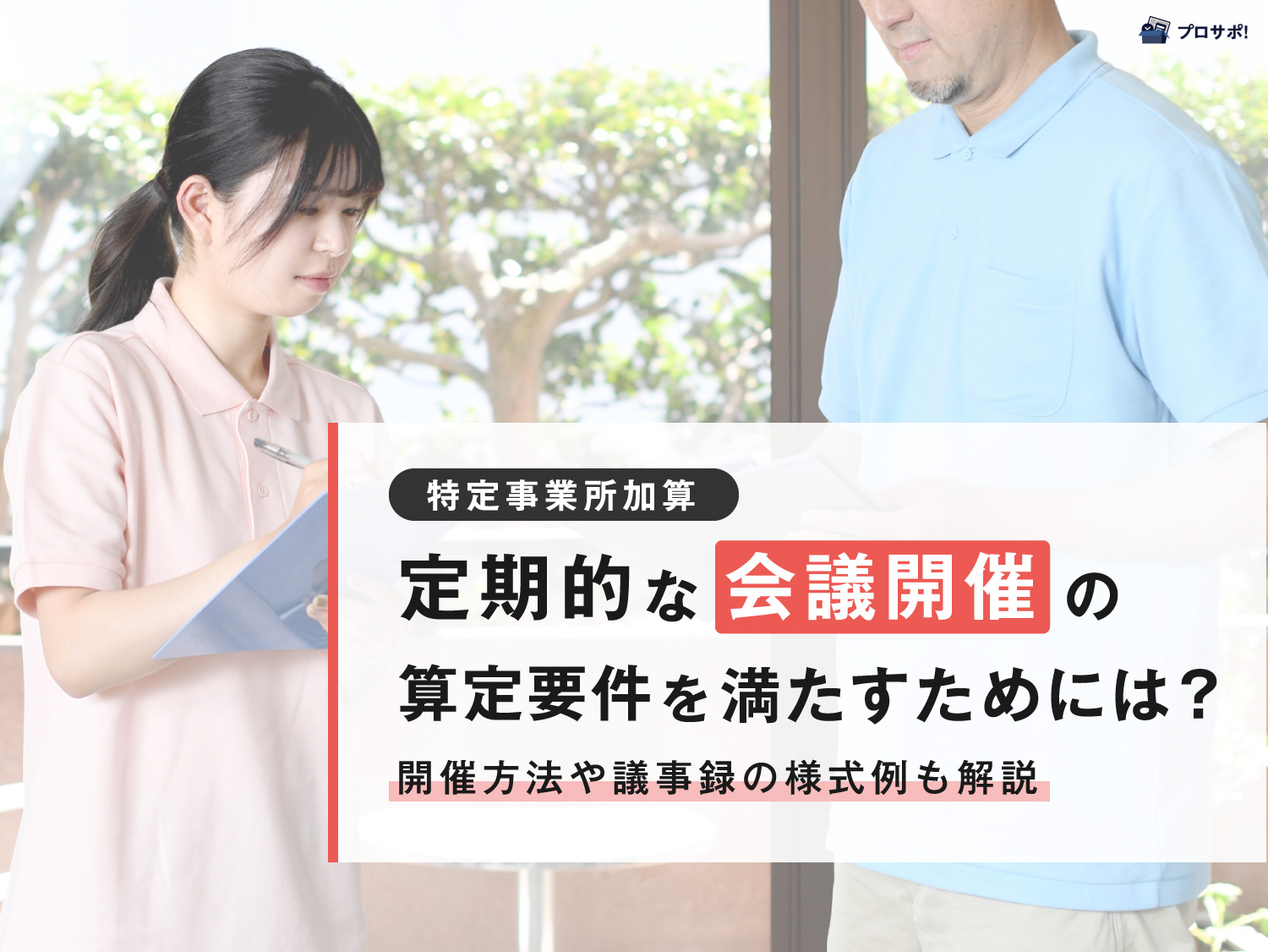
特定事業所加算
【特定事業所加算】定期的な会議開催の算定要件を満たすためには?開催方法や議事録の様式例も解説
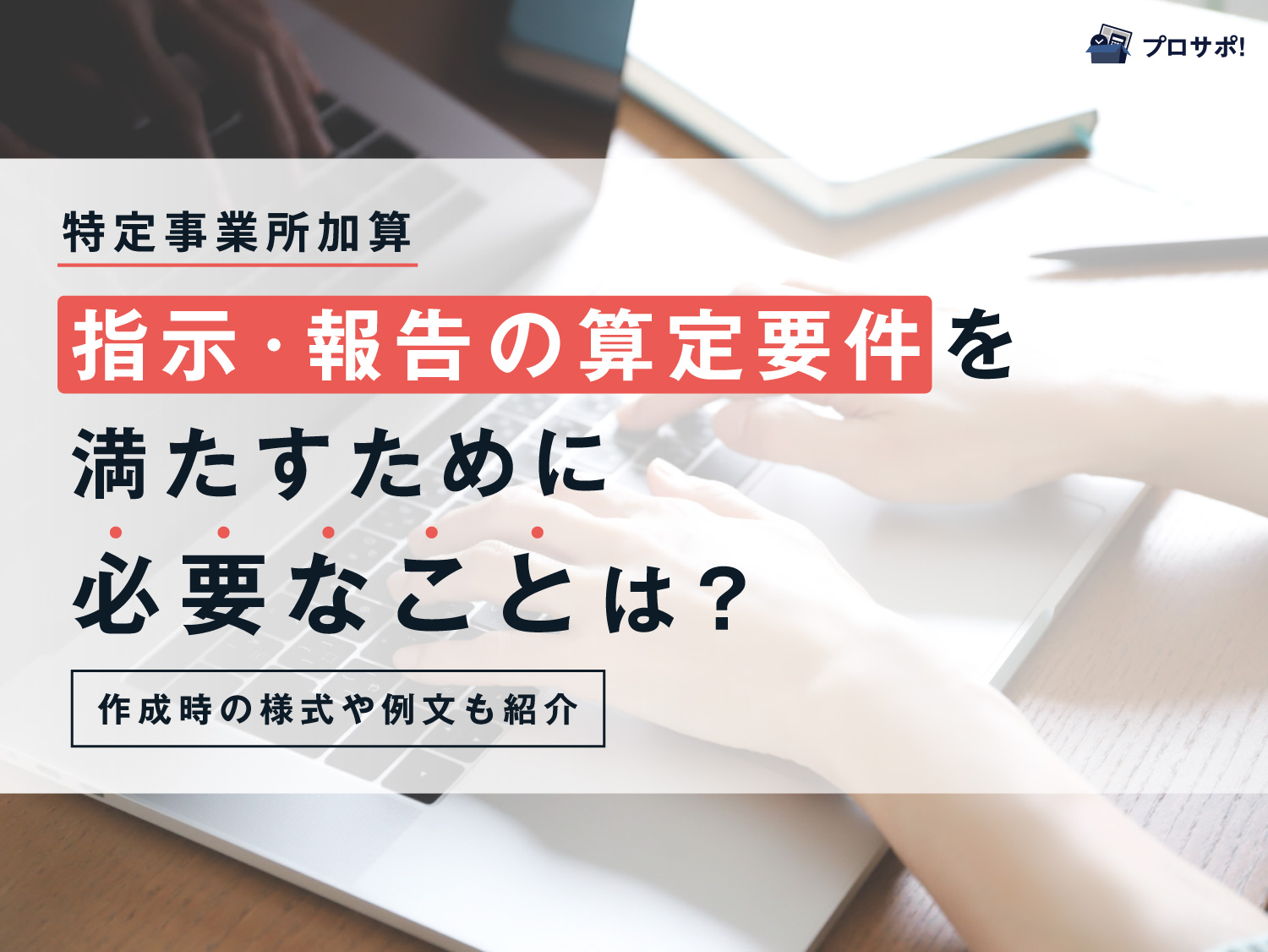
特定事業所加算
【特定事業所加算】指示・報告の算定要件を満たすために必要なことは?作成時の様式や例文も紹介

特定事業所加算
【特定事業所加算】健康診断の要件を満たす4つのポイントと注意点を解説

特定事業所加算
【特定事業所加算】緊急時の対応を利用者に明示するとは?4つのポイントを詳しく解説!

特定事業所加算
特定事業所加算を訪問介護で算定するデメリット3つ|質の高い事業所を目指そう

特定事業所加算
【令和6年度改定】特定事業所加算を重度訪問介護で算定するための要件とは?
サービスの詳細や
各種ご相談については
こちらから